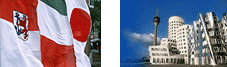広報文化
総領事館の文化行事 【 2008年 】
「日本酒セミナー」 2008年5月16日14時半~21時 |
|||
主催:日本酒造組合中央会、日本貿易振興機構(JETRO)、 在デュッセルドルフ日本国総領事館 於:総領事公邸 |
|||
| 御案内5月16日(金)、14時半から21時まで、総領事公邸主庭において、日本酒造組合中央会、日本貿易振興機構(JETRO)、総領事館の共催にて、「日本酒セミナー」を開催しました。このセミナーには、政府関係者、文化関係者、日本食関係者、経済関係者、当地在留邦人、当地プレス等約300人が訪れました。 |
|||
写真左から:柚岡JETRO所長、上野氏、マルクス・デル・モネゴ氏、ビュトフNRW州経済省局長 |
|||
最初に、増田泉彦・日本酒造組合中央会海外戦略委員長より、今回のセミナーが、日本で愛されている日本酒をドイツにおいて多角的に紹介する機会となることについて、感謝の挨拶が述べられました。続いて、柚岡一明JETRO所長より、日本酒は単に語ることではなく、試すこと(100回みるよりも1回飲むべき)が重要である旨挨拶され、丸尾総領事は、来賓の皆様に感謝を述べるとともに今回のセミナーの意義を述べさせて頂きました。 |
|||
|
|||
上野氏は、「日本酒案内」の講演で、日本酒の製造や日本酒の違い、更に、最近の日本酒紹介関連行事において、ドイツにおいて日本酒への関心が高まっていると述べていました。 |
|||
また、マルクス・デル・モネゴ氏(98年世界最優秀ソムリエ)からは、「日本酒と食事とのハーモニー、西欧料理と東欧料理とのふれあい」をテーマとして、講演を行って頂きました。マルクス・デル・モネゴ氏は、日本酒の「利き酒師」の資格も取得しておられます。講演では、専門知識に基づき、日本酒とワインの共通性や日本酒の料理との相性について多くの実例を挙げながら説明されました。更に、デル・モネゴ氏は、「日本酒やワインは、その国の文化を垣間見ることができるものであり、また、日本酒は水と米、ワインは土地といったその国の環境により特色づけられる。更に、違いを見いだす際には、甘さ、酸味、ミネラルの含有、酵母、苦み、様々なエキス、アルコール等が要素となる。ワインも、日本酒もその国の食卓の文化(テーブルマナー、食器等)にとって重要な要素である」と述べていました。また、日本酒は日本食とともに西欧料理とも組み合わせることができるとして、ワインと同様に、食事の際には、料理との味わいの組み合わせが理想的になるような日本酒を選ぶことが重要となると述べていました。具体例として、酸味を多く含んだ日本酒は、油を使った、あるいは、脂身の多い料理に合う、オマール海老には、花の香りがする純米大吟醸が理想的、ヤマドリダケ(Steinpilzen)のリゾットには、濃厚な日本酒、そして、軽い、新鮮なヤギのチーズにはエレガントで酸味の少ない日本酒が合うと述べていました。また、日本酒が含んでいる「うまみ」成分は、それ自身が、心地よい味わいであるのみならず、苦さや塩気と相まって深みのある味わいを引き出すと述べていました。 |
|||
増田泉彦・日本酒造組合中央会海外戦略委員長からは、「日本の四季と蔵元の営み」をテーマに、一年を通じて如何に日本酒造りが行われるかに関する講演を行って頂きました。増田氏は、京都で14代、330年続く蔵元です。具体的には、9月から10月の稲刈りから春まで行われる製造過程、また、発酵から瓶詰め、市場への販売、日本酒の製造過程における蔵元の社会風習、環境などにおける役割など経験に基づいて説明されました。最後に、「毎年、同じ花は咲くが、人は毎年変化する」という中国のことわざを引用しておられました。その意味は、「酒造りのプロセスは毎年同じであるが、酒を造る人は毎年変化する、そして、日本酒を愛好する人々も時とともに変化していく」とのことです。 |
|||
セミナーの参加者は、講演の間に、端麗な日本酒、濃厚な日本酒、古酒等様々な日本酒の試飲、日本からの蔵元との懇談、特に「酒祭り」の部では、寿司や日本食を楽しみながら、日本酒と料理の組み合わせを楽しんでいました。更に、日本酒を通じて日本人とドイツ人の懇談、意見交換等の交流が図られていました。参加者の多くが、今回のセミナーで、日本酒の製造方法、様々な味わい、料理との組み合わせの可能性、日本文化の中での日本酒の意義等に関する知識を持たれたと思います。今後、日本酒セミナーに来られた方々が、日本酒に関する知識を深め、より日本酒を愛好して頂くことを期待しております。 |
|||
今回、御協力頂きました日本酒造組合中央会、日本貿易振興機構(JETRO)に感謝申し上げます。特に、小桧山俊介・日本酒輸出アドバイザーには最初の準備段階から開催まで全ての面で御尽力頂き、感謝申し上げます。 |
|||
更に、当地を訪問された12の蔵元の方々(飯沼本家(千葉県)、高砂酒造(北海道)、竹の露(山形)、下越酒造(新潟)、白瀧(新潟)、三輪酒造(岐阜)、中島醸造(岐阜)、増田徳兵衛商店(京都)、辰馬本家(兵庫)、丸本酒造(岡山)、利守酒造(岡山)、天吹(佐賀))には、訪独の上、大変な御協力を頂き、改めて感謝申し上げます。 |
|||