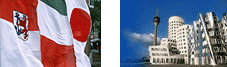丸尾総領事:
貴方は1998年にウィーンのコンテストで「世界最優秀ソムリエ」に輝き、同年に日本で日本酒の利き酒師の資格を取得しました。2003年以来、貴方は「マスター・オブ・ワイン」の称号もお持ちです。日本酒にいつから興味をお持ちになり、なぜ日本酒をテーマとして取り組むことになられたのかご説明いただけますか。
デル・モネゴ:
きっかけは1995年に日本で開催されたソムリエ世界選手権への準備でした。飲み物がテーマになった場合、ソムリエとして日本酒に関して質問されるだろうと思っていたからです。私は当時、ドイツで入手できる日本酒を購入し、いろいろと試飲してみたのですが、日本酒に最初から特別に魅了されていたわけではありません。しかし1995年、ソムリエ世界選手権のため日本を訪問し、そこで日本酒の試飲に参加した際に、私はこれまでとは全く異なる体験をしました。私は、異なった年代、辛口から甘口、まろやかな品質等様々な種類の日本酒を試飲し、新たな、魅力的な日本酒の世界を知ることになりました。上質の酒が含んでいる良質な香りにとても強い感銘を受けました。また、私達は最高級の日本酒だけを試飲しましたが、それらは、ワインと同じように複合的な香りをもたらしていました。日本酒と関連する文化や歴史全体が魅力的でしたが、そこからヨーロッパにおける文化の原動力、あるいは文化を形成する要素であるワインと日本酒との共通点を見出しました。1995年にドイツで購入できた日本酒は特定名称酒(精米度や製造方法において様々な規制が設けられている種類の日本酒)ではなく、発酵させた日本酒にぶどう糖をまぜたもの(普通酒)のみが取り扱われていて、日本酒の宣伝にはそれほど大きな役割を果たすものではありませんでした。
1998年に世界選手権が開催されるにあたって、私は日本酒が再びテーマとして取り上げられると確信しました(1995年の世界選手権では日本人が優勝)。私はこのテーマに一層深く打ち込むようになり、多くの英語文献を読み、日本酒、そしてこの飲み物の歴史的背景についてのより深い知識を得ました。1998年の世界選手権祝勝パーティーで、日本のある雑誌出版社が接触してきて、「酒・スペシャル」という企画を作るために、当時ソムリエ世界チャンピオンであった私を日本に一週間招待してくださいました。私たちは20種類の年代別の日本酒の試飲会に参加し、また、製造過程を注意深く観察することが出来ました。また日本酒に関連する儀式についても学ぶことができました。例えば、新しい酒樽を開けるセレモニーがありますが、これは出席している客に大きな名誉を与えるものです。杉の器で新鮮な酒を楽しむことは磁器の器やガラス製のコップで飲むこととはまるでちがいます。私にとって日本酒とは文化的に大きな価値を持つものです。私たちが西洋文化の中で度々ワインを定義したり、異なる種類のワインやぶどうを比較しますが、同様のことが、日本酒の場合でも当てはまると思います。私にとって、ある国の人々が何を食べ、何を飲んでいるかを知ること、また、それ以上にその国の文化を知り、理解することは非常に重要です。なぜなら、1995年以来、私は日本の食文化にも魅了されているからです。