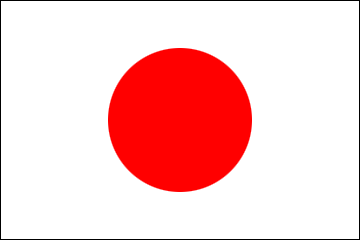ケンペルとレムゴについて
平成28年9月28日
ケンペル(Engelbert Kaempfer; エンゲルベルト・ケンプファー)と言えば、江戸時代に長崎の出島でオランダ東インド会社の医師として2年間過ごし(1690~1692)、著書「日本誌」によってのちのジャポニスムに大きな影響を与えたということで歴史の教科書にも載る有名人であるが、そのケンペルの出身地がレムゴ(Lemgo)という、今日では人口4万人ほどの都市であるということは、こちらに来るまで知らなかった。
そのレムゴというのがまた面白い町である。
まず、この一帯はリッペ(Lippe)という地方なのだが、レムゴの街並みは、笛吹き男で有名な「メルヘン街道」沿いのハーメルン(Hameln)と同じ「ヴェーザー・ルネサンス」様式で、ハンザ同盟に属す商業都市として中世から繁栄した。つまり、文化的にはデュッセルドルフのあるラインラントとは異なり、ブレーメンやハンブルクとのつながりの方が強い。
ノルトライン・ヴェストファーレン(NRW)州が70年前に英国の占領下で作られた半年後に、リッペ地方が住民投票の結果としてNRW州の最東端の行政区となった。
中世の魔女裁判が盛んにおこなわれていたということで、レムゴには魔女裁判の歴史についても非常に詳しく残されている。ケンペルが最終的に日本に行くことになる世界旅行に出るのも、レムゴで行われていた魔女裁判と関係がある、ということで、何が歴史を作るかという点では類稀なケースであると言えるかもしれない。
そのケンペルが死んだのが、今からちょうど300年前なのだそうで、それに因んだ展覧会のオープニングが9月9日にレムゴの「魔女市長の家」で行われることになり、その式辞を述べることになった。
ケンペルが日本で購入したと思われる300年前の日本各地の名所を描いた風景画が比較的最近になって大英博物館で発見されたのだそうだ。うち25枚を複製したものが展覧会の主役である。複製か、などと言うなかれ。300年前の日本の名所の風景画がドイツの地方都市で展示されているのである。
アウスターマン市長は、開会挨拶の中で、ケンペルの今日的意味を強調した。つまり、ケンペルは異文化に対し常に敬意をもって対応し、その土地の文化と融合していた、今日ドイツに移民先を求める人々にとっても模範となる、という訳である。
その比較が合理的かどうかはともかく、日本では歴史上の人物と考えられているケンペルは、レムゴでは郷土の偉人として、依然として身近に感じられているのである。そして、ケンペルが日本に残した足跡もまた、今日でも確かに刻まれている。
そのレムゴというのがまた面白い町である。
まず、この一帯はリッペ(Lippe)という地方なのだが、レムゴの街並みは、笛吹き男で有名な「メルヘン街道」沿いのハーメルン(Hameln)と同じ「ヴェーザー・ルネサンス」様式で、ハンザ同盟に属す商業都市として中世から繁栄した。つまり、文化的にはデュッセルドルフのあるラインラントとは異なり、ブレーメンやハンブルクとのつながりの方が強い。
ノルトライン・ヴェストファーレン(NRW)州が70年前に英国の占領下で作られた半年後に、リッペ地方が住民投票の結果としてNRW州の最東端の行政区となった。
中世の魔女裁判が盛んにおこなわれていたということで、レムゴには魔女裁判の歴史についても非常に詳しく残されている。ケンペルが最終的に日本に行くことになる世界旅行に出るのも、レムゴで行われていた魔女裁判と関係がある、ということで、何が歴史を作るかという点では類稀なケースであると言えるかもしれない。
そのケンペルが死んだのが、今からちょうど300年前なのだそうで、それに因んだ展覧会のオープニングが9月9日にレムゴの「魔女市長の家」で行われることになり、その式辞を述べることになった。
ケンペルが日本で購入したと思われる300年前の日本各地の名所を描いた風景画が比較的最近になって大英博物館で発見されたのだそうだ。うち25枚を複製したものが展覧会の主役である。複製か、などと言うなかれ。300年前の日本の名所の風景画がドイツの地方都市で展示されているのである。
アウスターマン市長は、開会挨拶の中で、ケンペルの今日的意味を強調した。つまり、ケンペルは異文化に対し常に敬意をもって対応し、その土地の文化と融合していた、今日ドイツに移民先を求める人々にとっても模範となる、という訳である。
その比較が合理的かどうかはともかく、日本では歴史上の人物と考えられているケンペルは、レムゴでは郷土の偉人として、依然として身近に感じられているのである。そして、ケンペルが日本に残した足跡もまた、今日でも確かに刻まれている。